「お米の値段、高すぎると思いませんか?」
その裏には、私たち消費者が知らない“中抜き地獄”が隠されていたという話が・・・
JAと5次問屋が築く多重搾取の構造――あなたの食卓が犠牲になっているかもしれません。
📝この記事を読むとわかること
- JAが「中抜き」と言われる理由
- 「5次問屋」ってどういうこと?
- なぜ農家の利益が少なくなるのか
- 今後、どんな改善があるのか
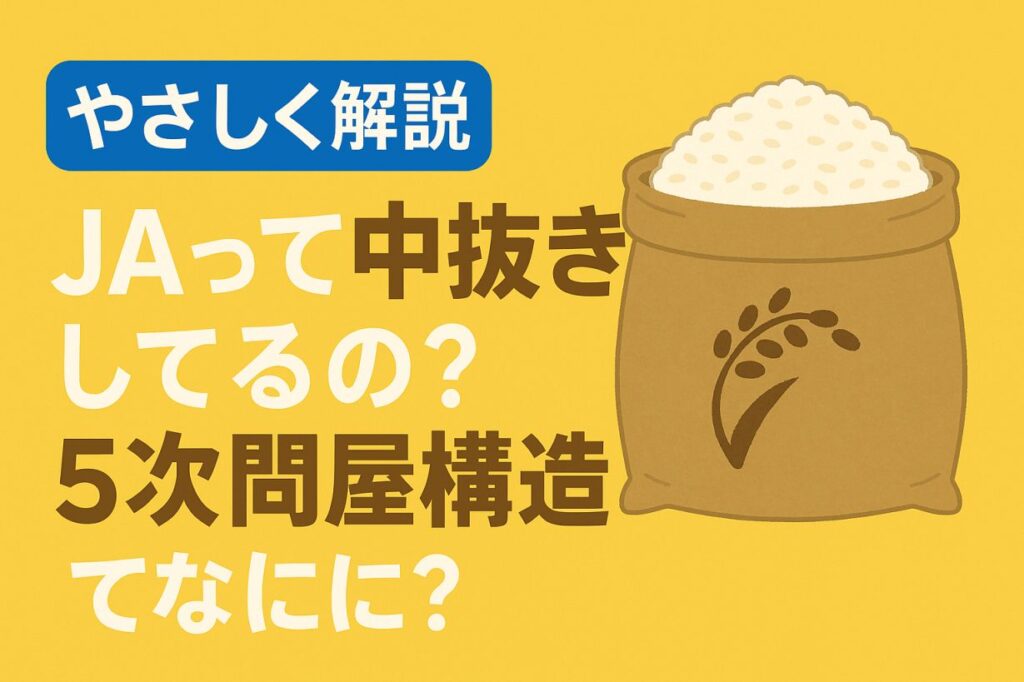
JAとは?まずここからスタート!
JA(ジェイエー)は「農業協同組合(のうぎょうきょうどうくみあい)」のことで、日本全国の農家が参加しているグループです。農家が作ったお米や野菜を、集めて出荷したり売ったりしてくれます。
農家の味方であるはずのJAですが、最近では「中抜き(なかぬき)が多すぎる」「農家にちゃんとお金が届いてない!」という声があがっています。
「5次問屋」ってなに?なぜ中抜きが多いの?
「5次問屋(ごじといや)」というのは、農家 → JA → 卸売 → 仲買 → 小売店 → 消費者…と、なんと5つ以上も業者を通してやっとお店に届くことを意味します。
そのたびに、
- 手数料(てすうりょう)
- 運送料(うんそうりょう)
- 倉庫の管理費(そうこのかんりひ)
などのお金がかかります。
つまり、農家が100円で売った野菜が、消費者には200円以上で売られているのに、農家にはその100円すら届かないこともあるんです。
どうしてそんなことになるの?
JAでは、農家から野菜をまとめて集めて、「選別(せんべつ)」「箱づめ」「出荷(しゅっか)」などをします。その作業にかかる費用として、
- 販売手数料(10~15%)
- 包装料(5~10%)
- 輸送手数料(5%)
などが差し引かれます。
さらに、その後の流通でもどんどんマージン(もうけ分)が上乗せされていくので、農家の手取りが減っていくのです。
なぜ問題なの?何がまずいの?
この仕組みの何が問題かというと…
- 農家が頑張っても収入が増えない
- 消費者は高いお金を払って買っている
- 野菜が無駄に高くなってしまう
これでは、農業を続ける人が減ってしまいます。実際、若い農家のなり手が少ないのは、こうした利益の少なさも原因の一つです。
解決策はあるの?
最近は、この「中抜きだらけの流通構造」を変えようという動きも出てきました。
✅ 直販(ちょくはん)
→ 農家が自分でネットや道の駅で売る
✅ スマホアプリの活用
→ JAを通さずに消費者と直接つながる仕組み
✅ 国の支援
→ 農家に直接お金が届く制度をすすめる
まとめ|JAの中抜き問題をみんなで知ろう!
日本の農業は、たくさんの人の力で支えられています。でも、その中で不公平な構造があるとしたら、それは見直す必要があります。
中学生のみなさんも、普段食べているごはんや野菜が、どんな人たちによって、どんな仕組みで自分の食卓に届いているのか、ちょっと気にしてみてくださいね。
【即完売続出】政府備蓄米が熱狂的人気!流通状況と今後の販売拡大の見通しを徹底解説
お米ってこれから安くなる?2025年の米価格と家計を守るコツ【やさしく解説】
おすすめのふるさと納税 米 定期便2025ランキング【最新版】
【Trend Navigator】今話題の急上昇キーワードまとめ





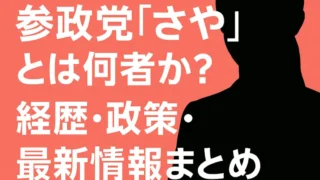


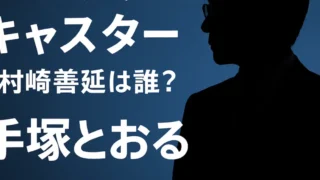

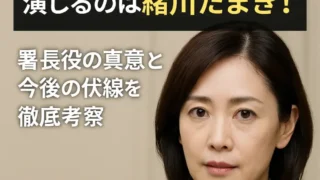

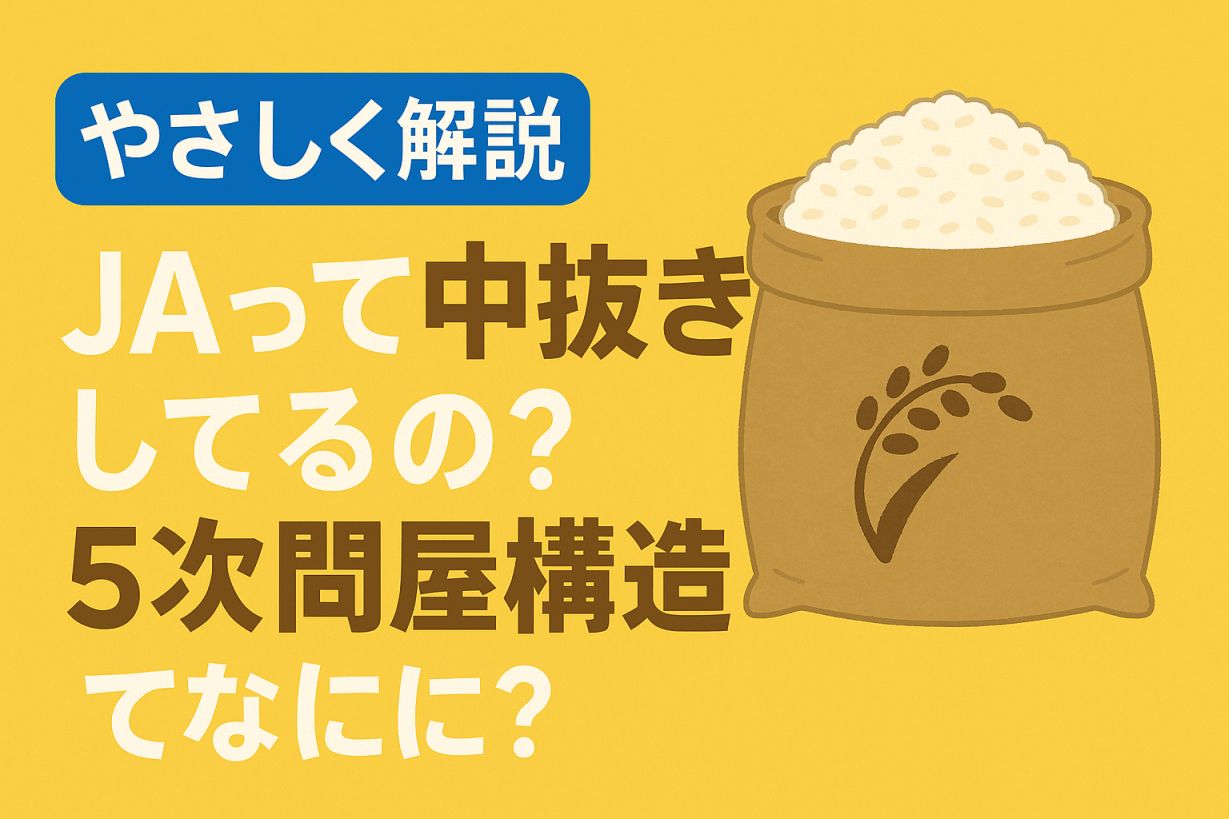

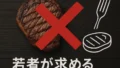
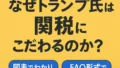



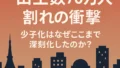
コメント