私自身ブラックな職場でうつ状態になりながらも、支えてくれたのは家族でした。子育てが一段落した今でも、常に感謝の気持ちを忘れていません。
しかし、社会は家族をつくり、子どもを育てる環境とはどんどん違う方向に進んでしまっています。
この記事を読むとわかること
- なぜ日本の出生数が想定より14年も早く70万人を割ったのか
- 少子化が加速している根本的な理由とその背景
- 社会保障制度や若者の経済不安との深い関係
- 今後の日本社会にどのような影響があるのか
- 解決へのヒントや対策の方向性
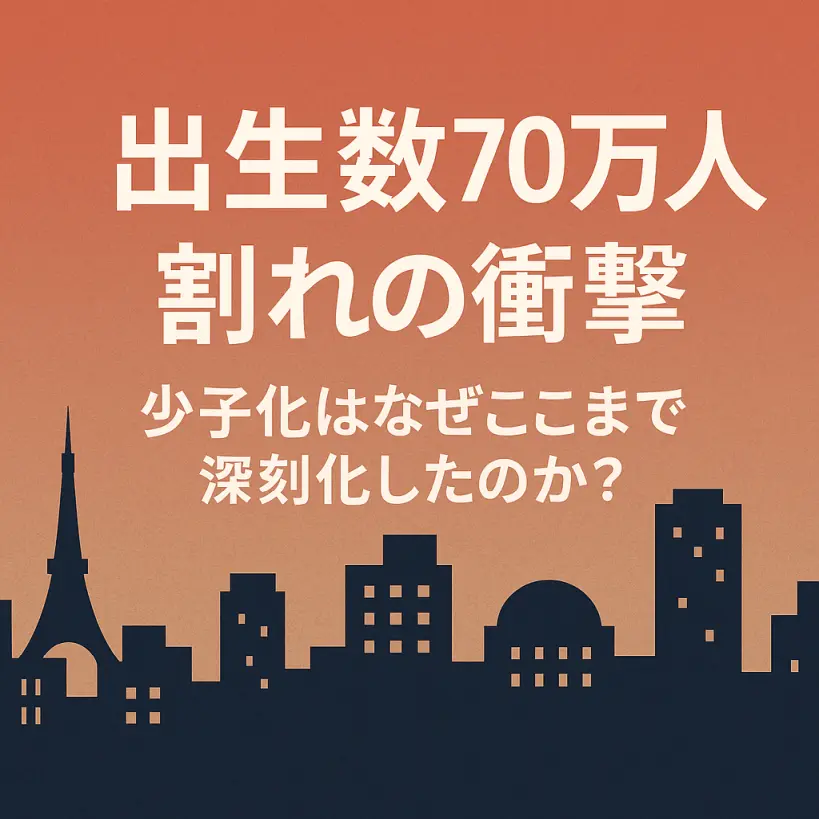
出生数70万人を下回る事態が14年も早く到来
2024年、ついに日本の出生数が70万人を下回った――。
これは国立社会保障・人口問題研究所がかつて想定していた2038年を14年も前倒しする、まさに想定外のスピードでの少子化進行です。
本来、2024年時点では75万人程度の出生数が見込まれていたはずでした。ところが、現実にはそれを大きく下回る結果となり、「少子化」が予測以上に深刻化していることが明らかになりました。
少子化がここまで深刻化した原因とは?
1. 若者の経済的不安が結婚・出産を阻む
最大の要因とされるのが、若年層の経済的不安です。
正社員になれない非正規雇用、低賃金、将来の生活設計の難しさ…。このような状況では「家庭を持つ」「子供を産む」という決断そのものが重荷となってしまいます。
藤波匠・日本総合研究所の主任研究員も、「低所得層ほど子供を持てない」と指摘し、最低賃金の引き上げや雇用環境の改善を訴えています。
2. 結婚適齢期を迎える世代の母数が減少
少子化は加速する一方で、これから結婚・出産を迎える世代の数自体が減っています。
1990年代生まれの出生数は120万人規模でしたが、2005年には110万人を下回り、2016年には100万人を割り込みました。
母数が減っていく中で、たとえ出産意欲があっても社会全体での出生数は確実に減っていく構造にあるのです。
社会保障制度に迫る危機
日本の社会保障制度は、「現役世代が高齢者を支える仕組み(賦課方式)」が基本です。
つまり、働く世代が減り続ける一方で、支えられる高齢者が増えていく――。このバランスが崩れれば、
- 年金制度の破綻
- 医療保険料の急激な上昇
- 子育て・介護支援の財源不足
といった問題が現実味を帯びてきます。
「制度の持続性が危ぶまれる段階に入った」との声もあり、出生数の低下はもはや個人の選択ではなく国家存続に関わる問題となっています。
地方の出生率低下と女性雇用の課題
一方で、都市部だけでなく地方の出生率も急激に低下しています。
その原因のひとつが、「女性の雇用の質と数の不足」。夫婦共働きが一般的になった今、地方で女性が安定して働ける場所がないと、「結婚しても子供を産めない」という現実に直面します。
地方創生や移住政策だけでは不十分で、女性が活躍できる職場の整備が急務です。
政府は“2030年までがラストチャンス”と警告
政府は「2030年までが少子化反転のラストチャンス」としていますが、これまで打ち出された政策(子育て給付金・保育無償化・婚活支援など)は十分な効果を上げられていません。
実効性ある施策とは?
- 若者の可処分所得を増やす
- 雇用の安定と正社員比率を上げる
- 女性・子育て世代の働きやすい社会整備
- 保育・教育環境の地域格差解消
政府・企業・社会全体が一体となって取り組む必要があります。
まとめ|未来に希望を持てる社会を
出生数が70万人を割ったという事実は、単なる「統計上の変化」ではありません。
社会が若者に将来の安心を与えられていないという、構造的な問題の表れです。
私たちはこの数字の裏側にある「生きづらさ」「不安」にもっと目を向けるべきです。
少子化を止めるには、まずは若者一人ひとりが「家庭を持ちたい」「子供を育てたい」と思える社会の実現が必要です。



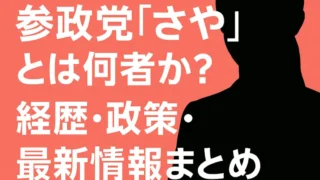


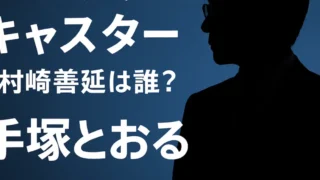
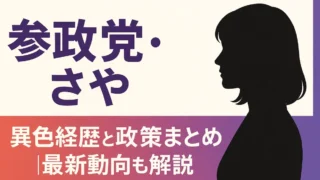



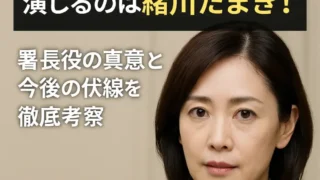


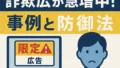

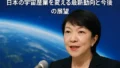

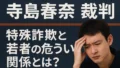
コメント