「お米が高すぎて買えない…」そんな状態でもう1年以上が経つでしょうか。
政府の備蓄米が尽きた場合、外国産米の緊急輸入が検討されています。
しかし、コメ不足の本当の原因は、50年以上続く減反政策にあるかもしれません。今こそ、私たちの食卓と農業政策の未来を考える時です。

コメ不足の背景と政府の対応
2025年6月6日、小泉進次郎農相は、コメ価格の高騰を抑えるため、政府備蓄米の放出が尽きた場合、外国産米の緊急輸入を検討していることを明らかにしました。
これは、1993年の冷夏による不作以来の措置となります。また、農家の経営を守るため、収入保険の活用も推進しています。
減反政策が招いた「令和の米騒動」
コメ不足の原因として、長年続く減反政策が指摘されています。
この政策は、コメの生産量を意図的に減らし、市場価格を維持することを目的としています。
その結果、需要のわずかな変動でも供給が追いつかず、価格が高騰する事態を招いています。
実際、2023年の作況指数は101と平年並みであり、不作ではありませんでした。
それにも関わらず、コメの価格は例年の2倍以上に高騰しています。
備蓄米を放出したのに高すぎる…コメ価格高騰がいつまでも終わらない根本原因
国民の声と求められる改革
ネット上では、「備蓄米を放出しても価格が下がらない」「減反政策を見直すべきだ」といった声が多く見られます。
また、「外国産米の輸入よりも、国内の生産体制を強化すべきだ」との意見もあります。
これらの声は、現行の農業政策に対する不満と、改革への期待を示しています。
今後の展望と私たちにできること
コメの安定供給と価格の適正化には、減反政策の見直しや、生産体制の強化が必要です。
また、消費者としても、国産米の価値を再認識し、適正な価格での購入を心がけることが求められます。
政府と国民が一体となって、持続可能な農業と食の安全保障を築いていくことが重要です。
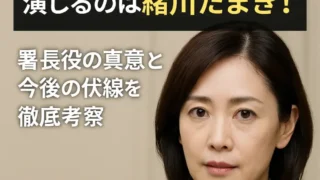



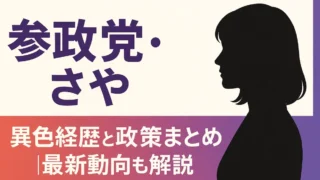




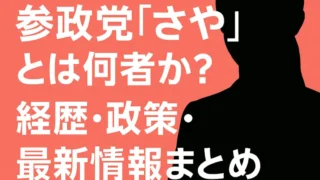
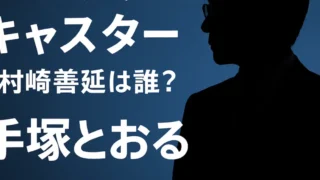


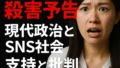
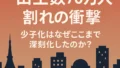
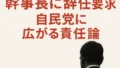



コメント