この記事でわかること
- AI生成詐欺広告とは何か、その特徴
- 実際に発生している事例
- AI生成詐欺広告が急増している背景
- 被害に遭わないための具体的な防御法
- 万が一購入してしまった場合の対応策
AI生成詐欺広告とは?
近年、生成AI技術を悪用した詐欺広告がSNSやYouTube、Google広告で急増しています。
従来の詐欺広告と異なり、生成AIを使って有名人の画像を自然に合成した広告や、高精度な製品レビュー動画を自動生成し、あたかも本物のように見せかけるのが特徴です。
さらに、
- 有名ブランド・公的機関のロゴ・画像を自然に合成
- 存在しないインフルエンサーによる「体験談動画」
- 偽物商品の実物画像を生成して広告に使用
などの手口が使われ、一般消費者が見抜くのが困難になっています。
実際に起きている事例
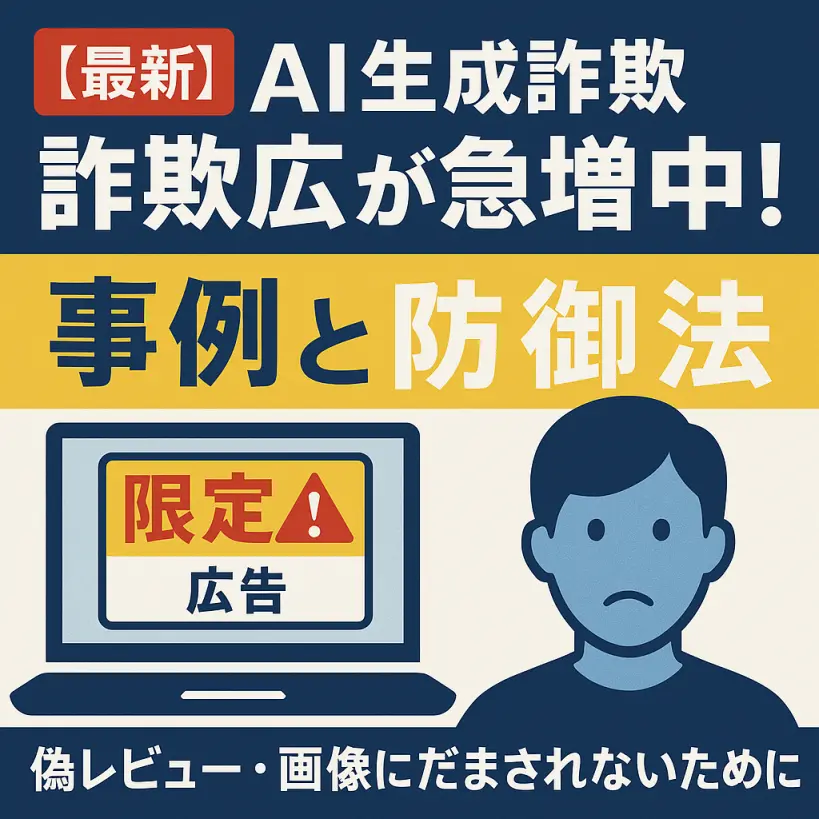
事例①:著名人の顔写真を合成した投資詐欺広告
AIで著名人が投資を勧めているかのような動画広告が流れ、多くの人が信じて送金し被害。
事例②:有名ブランドのロゴを使った格安家電販売
「AI冷却技術搭載」とうたう小型エアコンが広告され、実際には粗悪品が送られてくる被害が続出。
事例③:医師監修を装った健康食品広告
生成AIで作成した「医師が推奨する動画広告」をSNSで配信し、高額サプリを販売する詐欺。
なぜ今、AI生成詐欺広告が急増しているのか?
- 生成AIの進化で動画・画像の高品質化が容易になった
- SNS広告の審査が緩く、すぐに出稿可能
- 海外の詐欺業者が越境ECで日本市場を狙う
- 為替差・人件費差を利用し低コストで大量に広告を出せる
- 消費者が広告の真偽を確かめる機会が少ない
これらの背景により、AI生成詐欺広告は今後さらに巧妙化・増加する可能性が高いです。
AI生成詐欺広告を見抜くポイント
- 「限定」「残りわずか」「本日終了」など焦らせる表現に注意
- 公式サイトに商品情報が掲載されているか確認
- 不自然に高評価レビューばかりの場合は疑う
- 広告に登場する著名人が公式に発言しているか確認
- SNS広告は即購入せず、商品名+詐欺で検索する
万が一被害に遭った場合の対応
- 支払い方法ごとに対応
- クレジットカード:カード会社に連絡、チャージバック相談
- PayPal:紛争解決センターへ申請
- 銀行振込:振込先情報をもとに警察・消費生活センターへ相談
- 証拠保全
- 広告のスクショ・動画
- 購入履歴・メール履歴
- 届いた商品の写真
- 最寄りの消費生活センターへ相談
AI生成詐欺広告から自分を守るために
生成AI詐欺広告は便利さ・お得感・限定感を煽り、消費者の「すぐ欲しい気持ち」につけ込むのが特徴です。
「本当に必要か」「本当に安全か」を冷静に考え、購入前に調べる習慣を持つことが、被害を防ぐ最大の防御策になります。


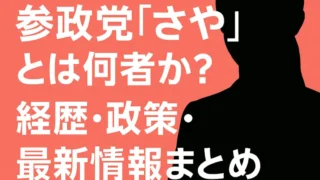



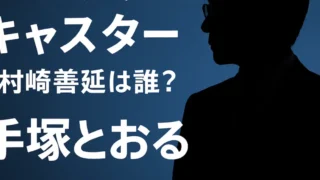


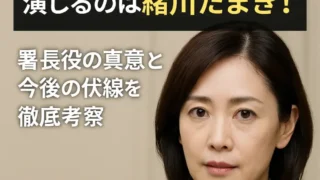


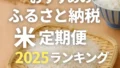

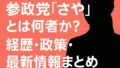

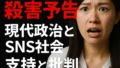

コメント