大切な人を見送るとき、私たちは「なるべく安らかな姿で」と願います。
そのための選択肢のひとつが「エンバーミング(防腐・整容処置)」です。
私自身、父を看取った際にこの処置を受けました。
しかし調べていくうちに、「全員にとって必要なわけではない」とも感じました。
この記事では、私の体験を軸に、エンバーミングのメリット・デメリット・判断基準をまとめました。
エンバーミングとは?簡単におさらい
- 専門技術者(エンバーマー)が行う、遺体の保存・整容処置
- 腐敗防止・感染症予防・表情・血色の修復が主な目的
- 欧米では標準的、日本ではまだ普及率20%未満(IFSA調べ, 2023)
実体験:私はエンバーミングを依頼しました
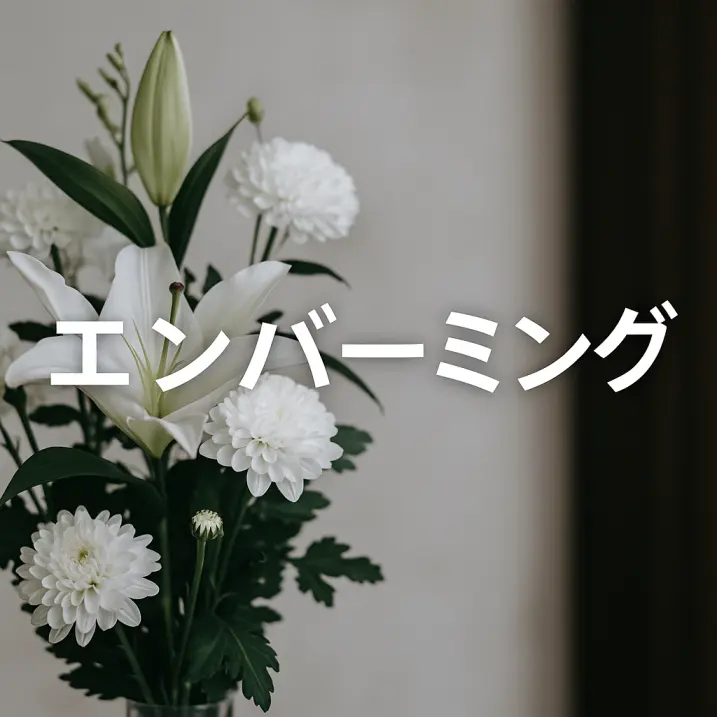
2024年、真夏の時期に父が亡くなりました。
火葬場の予約が取れず、葬儀まで5日空いてしまうことが判明。
葬儀社から「この時期、エンバーミングをしないとお体が変化する可能性があります」と言われ、依頼を決めました。
処置後、父は穏やかな表情で、家族も自然にお別れができました。
私は「やってよかった」と感じた一方で、後になって「必ずしも全員が必要なのだろうか?」と考えるようになりました。
メリット:エンバーミングを選ぶ価値がある場面
- 火葬まで日数が空く(3日以上)
- 高温多湿の季節(特に7〜9月)
- 家族が遠方にいて面会日がずれる
- 安置を自宅で行いたい
- 安らかな表情で見送りたい
こうした条件が重なる場合、エンバーミングは非常に有効です。
では、なぜ「慎重に検討すべき」なのか?
ここからは、私が調べた上で気になったデメリットや懸念点を正直に紹介します。
エンバーミングのデメリット・注意点
1. コストが高い
- 一般的に 10〜20万円前後
- 葬儀全体の費用が膨らむ
- 保険適用なし(自費)
2. 不要なケースでも勧められることがある
- 寒冷地や冬季であれば冷却でも十分対応できる
- 火葬までの日程が早ければ、必要性は低い
- 密葬や面会不要なら見た目の配慮も不要
実際、知人は「冬・2日後に火葬・面会なし」という状況でエンバーミングを勧められたものの、断って問題なかったそうです。
3. 遺体への処置に抵抗を感じる人も
- 体液の排出や血管からの注入など、技術的には「侵襲的処置」
- 宗教や文化的理由で避けたい人も
- 「自然のままの姿で見送りたい」という考えに合わない場合もある
4. 情報不足による納得感の欠如
- 説明が簡素で、選択肢としての理解が浅いまま依頼してしまう
- 家族内での意思確認不足からトラブルに発展することも
私の提案:「判断基準」を持とう
以下の5つの問いを、考えてみてください:
- 火葬まで何日空く予定か?
- 季節・気温はどうか?
- 面会の有無・日程は?
- 表情を整えることが自分にとって大事か?
- 葬儀社の説明は十分だったか?
この問いに「はい」が多ければ、エンバーミングは前向きに検討すべき選択肢だと思います。
よくある質問(FAQ)
Q. 衛生的に問題ないのですか?
→ 専門施設で処置されるため衛生管理は徹底されています。
Q. 費用が高く感じます。値引きはある?
→ プランによってはセット割引などがあるため、葬儀社に確認を。
Q. 処置を断って後悔することもありますか?
→ 状況によります。後悔を防ぐためにも、事前に他の選択肢(冷却・ドライアイス対応)も理解しておきましょう。
結論:必要な人にとっては救い、でも万能ではない
エンバーミングは、大切な人の最期を「丁寧に見送る」ための選択肢の一つです。
私はやってよかったと感じましたし、他のご遺族の気持ちにも配慮できるものだと感じました。
でも、それが「正解」かどうかは人それぞれ。
季節・状況・価値観によって、不要なケースも確かにあるのです。
正しく知り、自分たちに合った選択をすること。
それが最も後悔の少ない見送り方につながるのではないでしょうか。


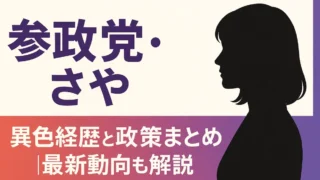

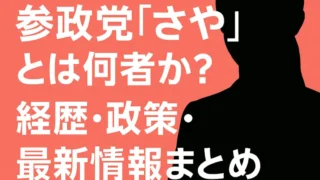



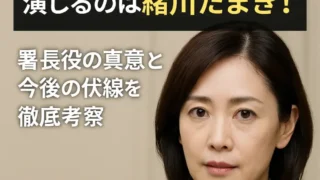

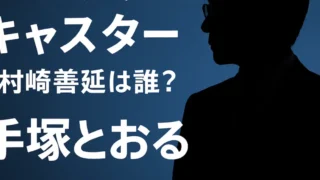


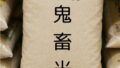
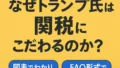
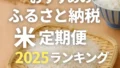

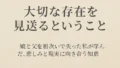

コメント