人生において、「別れ」は突然訪れます。
2023年、私は最愛の娘を亡くし、翌年には91歳の父を見送りました。
ほんの短期間のあいだに、かけがえのない2人の存在を失い、私はいまだに深い喪失の中にいます。
この記事では、私自身の経験をもとに、「心の準備ができないまま迎えた別れ」にどう対応したか、
そして、悲しみと現実の両方に向き合うために努力したことをお伝えします。
心の準備ができていなかった私
娘の死がもたらした感情の波
娘の死は、まさに突然のものでした。
毎日が当たり前だったのに、その「当たり前」が一瞬で崩れ去った衝撃は、今でも忘れられません。
時間が経っても、涙は勝手に流れます。
買い物中でも、電車の中でも、歩道を歩いていても、ふとした瞬間に。
心療内科で主治医から言われた言葉が、今でも印象に残っています。
「時間が薬になるとは限りません。癒えない悲しみは、確かに存在します」
この言葉に、私はようやく「この気持ちのままでいいんだ」と思うように自分に言い聞かせています。
「普通の暮らし」が戻ってこない
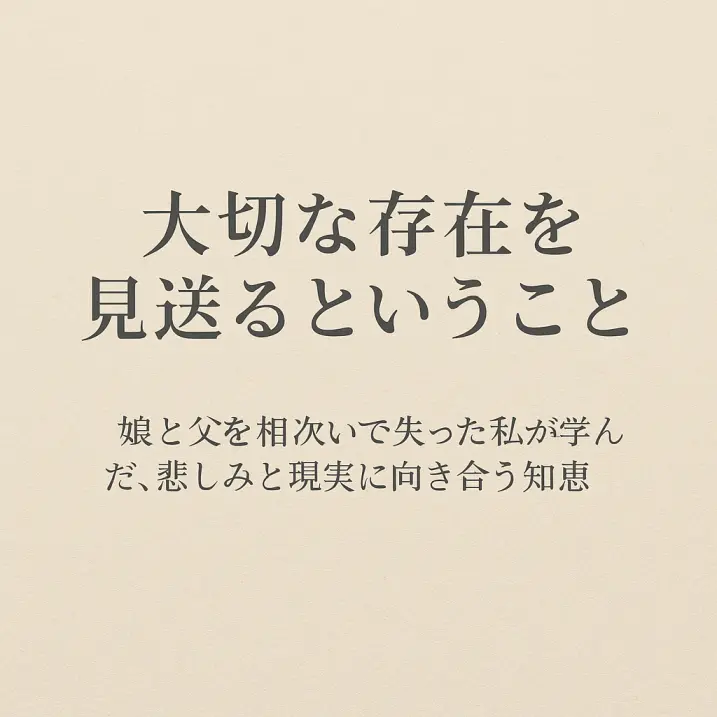
周囲の人たちは、悪気なく「少し落ち着いた?」と声をかけてきます。
でも私にとっては、「落ち着く」という言葉そのものが、まだ遠いところにあるのです。
- 朝、起きるのがつらい
- 食事の味がわからない
- 好きだった音楽が聴けない
そんな状態でも、現実は容赦なくやってきます。
父の死が教えてくれた「現実との向き合い方」
父は高齢でした。
老衰の兆候もあり、ある程度「覚悟」はしていました。
それでも、いざその日を迎えたとき、自分があまりにも無力であることを実感しました。
やらなければならなかった主なこと
- 施設からの連絡と死亡診断書の取得
- 市役所への死亡届提出
- 火葬許可証の申請(葬儀社が代行)
- 火葬場の空きがないため「エンバーミング処置」実施 詳しくは👉こちら
- 年金の停止(年金事務所に予約)
- 銀行口座凍結と引き落とし整理
- 相続準備(凍結タイミングに要注意)
時間的にも体力的にもギリギリでした。
悲しみに浸るどころではなく、ただ「やること」に追われました。
思い出が、より深く私を苦しめることもある
娘と一緒に暮らした日々。
猫を愛していた娘が、バスケットに花を敷き詰めて、亡くなった愛猫をそっと寝かせたあの日の光景。
その記憶が、今も私の心を強く締めつけます。
「思い出は宝物」とよく言いますが、
その宝物に触れるたびに、痛みが増すような感覚も確かにあります。
私が「心の整理」のために試したこと
1. 書くことで気持ちを形にする
私は毎晩、娘と父のことを書き続けました。
泣きながらタイピングした文章は、つらくて読み返すこともできません。
「今の自分はこんなふうに感じている」と言語化することは、苦しいものでした。
2. 距離をとることで自分を守る
人間関係を一度リセットすることもありました。
会うと必ず「娘さんどうしてますか?」と言いそうな過去の知人とは、ずっと距離を置いています。
それが正解かは分かりません。でも、「自分を守る」という意味では、必要なのだと思います。
3. 「何もできない」自分を受け入れる
朝散歩がいいと言われましたが、私には効果がありませんでした。
故人の好物を作って供えることも、行事を続けることも、今はまだできません。
「それでもいい」と思えるようには、まだなっていません。
救いになったのは、「自分以外にも同じ経験をした人がいる」と知ったこと
ある日、ネットで「日本では1日約3,900人が亡くなっている」という統計を見ました。
つまり、毎日3,900人の家族や大切な人が、喪失と向き合っているということです。
この現実に触れたとき、「私だけじゃない」と少しだけ思えました。
そして、この気持ちを誰かと共有したいと思うようになり、この記事を書くことにしました。
よくある質問(FAQ)
Q. 悲しみが何ヶ月も続いています。これはおかしいことでしょうか?
A. いいえ、正常です。子どもを失う悲しみは人生最大の痛みとも言われ、5年以上かかる場合も珍しくありません。
Q. 日常生活がうまく回りません。どうすれば?
A. 無理に「戻ろう」としなくていいと思います。できることを一つずつ。時には誰かに頼ってください。
Q. グリーフケアを受けたいのですが、どこで受けられますか?
A. 心療内科、自治体の相談窓口、遺族の会など、さまざまな支援があります。お住まいの地域名+「グリーフケア」で検索してみてください。
おわりに
この文章が、今まさに大切な存在を見送ったあなたの心に、少しでも寄り添うことができたなら幸いです。
悲しみは、「乗り越えるもの」ではなく「共に生きていくもの」。
それを忘れずに、私はこれからもゆっくりと、歩き続けていこうと思います。
もし、コメントやメッセージであなたの体験を教えてくださる方がいらっしゃれば、心から歓迎します。
関連記事
順次更新して参ります。


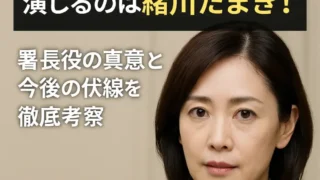





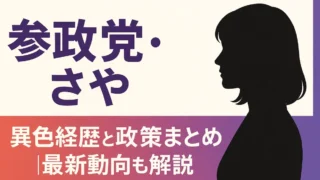
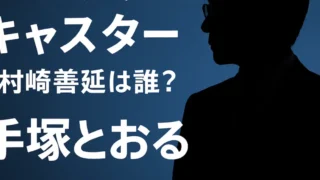

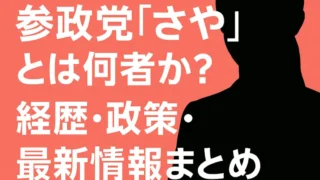
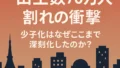
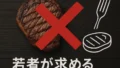



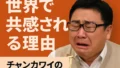
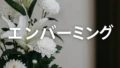
コメント